台所排水口つまりは自分で直す!予防&解消法で流れが悪い原因を撃退
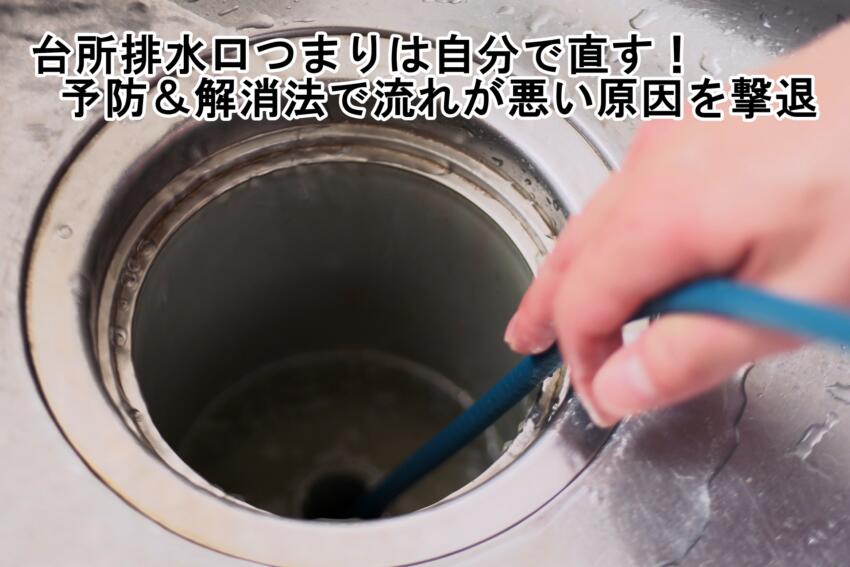
台所は、家の中でも特に使用頻度が高い水回りのひとつです。
そのため、排水口のつまりが起きやすい場所でもあります。
使用回数が多いほど、油や食べカスなどが溜まりやすく、つまりのリスクが高まります。
排水口がつまると、台所が使えなくなり、日常生活に大きな支障をきたすことになります。
できるだけ早く改善することが求められます。
多くの場合、排水のつまりが発生すると水道業者に修理を依頼することになりますが、必ずしもすぐに対応してもらえるとは限りません。
そんなとき、自分でつまりを解消できれば、最も早く元の生活に戻ることが可能です。
この記事では、台所の排水口がつまったときの対処法や、つまりを予防するためのポイントについてご紹介します。
台所排水口の流れが悪くなる3つの主な原因
一口に「台所排水口つまり」と言っても何処でつまっているかによって解消方法も変わってきます。
台所の排水はシンクの排水口からトラップを通り、蛇腹ホースを通り、床下の排水管を通って排水桝へと流れて行きます。
それではよくつまりが起きる3つの原因を解説して行きます。
- 排水口目皿つまり
- トラップ部つまり
- 排水管、排水桝つまり
それでは各場所のつまりの特徴を見て行きましょう。
【発生頻度No.1】排水口の目皿つまり
台所の排水口には「目皿(めざら)」が設置されており、シンクで発生する食材カスやゴミが排水管へ流れ込むのを防ぐ役割を担っています。
この目皿には日々の調理で出るさまざまなゴミが溜まりやすく、放置すると流れが悪くなってしまいます。
排水口の中で、一番手前に位置するのがこの目皿であり、つまりが発生しやすい場所です。
しかし、ここで発生するつまりは比較的軽度なもので、目皿に被せたネットを交換したり、目皿自体を清掃するだけで簡単に改善できるケースがほとんどです。
日常的にゴミが溜まりやすい箇所だからこそ、こまめな清掃がつまり予防の第一歩となります。
知らぬ間に汚れが溜まる排水口のトラップ部分

トラップとは溜まっている水(封水)で下水からの悪臭や虫などが室内に侵入するのを防ぐ為の機能です。
台所で言えばシンクの排水口にトラップのある「椀トラップ」か、シンク下にトラップがある「S字トラップ」、またシンク周りにトラップは無く、排水桝にトラップがある「トラップ桝」という種類があります。
中でも圧倒的に設置が多いのは排水口にトラップがある椀トラップタイプとなります。
トラップ部分は排水の流れが遅くなる為、つまりが起こりやすくなっています。
台所以外も危ない!排水管や排水桝のつまりとは?

目皿や排水トラップを点検・清掃しても水の流れが改善しない場合、原因がさらに奥の排水管や屋外の排水桝にある可能性が高くなります。
■ 排水管のつまり
排水管は建物の床下を通っており、台所で使った水や汚れはここを通って外へ流れていきます。
しかし、以下のような条件が重なると、汚れが沈殿し、つまりが発生しやすくなります。
- 排水管の勾配が適切に取られていない
- 横引きの距離が長い(直線で流れにくい)
このような環境では、水の流れが弱まり、油や食材カスが管の中に残りやすくなってしまいます。
■ 排水桝のつまり
排水桝(はいすいます)は、屋外に設けられている点検口で、複数の排水管の合流地点にあたります。
ここでも水の流れが弱くなると、油分や汚れがたまり、つまりの原因になります。
特に、台所の排水が「トラップ桝」へ直接流れているタイプの場合は、トラップ機能により水の流れがさらに遅くなる構造のため、つまりが起きやすくなります。
なお、これは台所だけに限った問題ではなく、お風呂や洗面所など他の水回りにも共通するトラブルです。複数箇所で排水不良が見られる場合は、屋外の排水桝や排水管全体を点検する必要があります。
排水口に何がつまる?台所で原因となる物質ランキング
台所でつまりが発生しやすい場所を見てきましたが、次は物質的にどのようなものがつまるのかを見て行きたいと思います。
つまり物質ランキングのベスト3は以下の様になります。
| 順位 | つまりの物質 |
| 第1位 | 油・脂成分の沈殿物 |
| 第2位 | 食材カスや残飯 |
| 第3位 | 食器やスポンジ |
それでは、第3位から詳しく見て行きましょう。
第3位 掃除中にうっかり!食器やスポンジなどの物落とし

排水口の掃除中や日常のキッチン作業中に、うっかりスプーンや箸、スポンジなどを排水口に落としてしまうことがあります。
これらの異物は当然ながら排水の流れを妨げ、つまりの原因となります。
■ 金属製のカトラリー(箸・スプーン・フォークなど)の場合
こうしたアイテムは重さや長さがあるため、排水口から奥の床下の横引き排水管まで流れていくことは稀です。
しかし、縦の排水管から横引き管へ切り替わる曲がり角(エルボ部分)などに引っかかることがあり、ここでつまりを引き起こすケースがよくあります。
■ スポンジやスポンジ片の場合
スポンジは軽く柔らかいため、排水管の内部に入り込みやすく、さまざまな場所で引っかかる可能性があります。
- 排水栓のパイプ部
- 蛇腹ホース
- S字トラップなどの狭い部分
特に、スポンジを切って使っていた場合は、小さな断片が流れてしまうこともあります。
パイプより小さいサイズであればそのまま流れてしまうこともありますが、排水管内や排水桝に溜まった汚れに引っかかって、大きなつまりの原因になる可能性もあります。
第2位 気を付けても排水口に流れてく細かな食材カスや残飯

台所のつまり原因として多いのが、食べ残しや生ゴミなどの食材カスです。
どんなに注意していても、日常的に食器を洗う中で小さな食べカスが排水口に流れ込み、排水管の内側に少しずつ汚れが付着していくことがあります。
通常、台所の排水口には「目皿」が設置されており、大きなゴミが排水管まで流れ込むのを防いでいます。
しかし、以下のようなケースでは、目皿の機能が不十分となり、つまりの原因になることがあります。
■ つまりを引き起こしやすいケース
- 目皿がそもそも設置されていない
- 掃除や作業のために一時的に目皿を外したまま使用した
- 目皿を戻したつもりでも、位置がずれて隙間ができていた
このような状態で食材カスが直接排水口に流れ込むと、ぬめりやヘドロの原因になります。
見た目はきれいでも、排水トラップの内部やネットの網目、配管の内壁にぬめりが蓄積し、最終的には排水不良や完全なつまりへとつながってしまいます。
第1位 調理や洗い物の際に流れ出る油・脂成分のつまり

台所で調理をした後、使用済みの油を適切に処理していても、フライパンや食器に残った調理油や食材の脂分は、どうしても排水口に流れ込んでしまいます。
これらの油脂成分は水と混ざりにくく、排水管の中に少しずつ蓄積されていきます。
さらに、油脂は冷えると固まる性質があるため、排水管内で冷やされることで固形の油の塊へと変化し、やがてつまりを引き起こします。
このようにして形成された油の塊は、水の流れを妨げる原因となり、排水不良や逆流、悪臭の原因にもなります。
特にこの油・脂分によるつまりは台所特有の問題であり、台所排水口のつまり原因として最も多いトラブルとされています。
自分で台所の排水口つまりを解消する3つの方法
台所排水口つまりは自分で直せるに越したことはありません、自分で解消することができれば時間的にも費用的にも一番ストレスがありませんので。
それでは自分で台所排水口つまりを解消する3つの方法をご紹介します。
- お湯とタオルで出来るつまり解消法
- 市販洗剤でつまりを直す効果的なテクニック
- ラバーカップを正しく使ってつまりを直す方法
今回ご紹介する3つの方法は比較的に簡単な解消法なので、男女問わずに実践することができます。
お湯とタオルで出来る排水口のつまり解消法

お湯とタオルを使う方法はお湯の熱と水量・水圧を使ってつまりを解消する方法です。
お湯を使うことで、冷えて固まった油分が溶けやすくなり、大量のお湯を一気に流すことによってつまりを溶かし流します。
使うものはお湯とタオルのみなので、とても簡単な解消法となります。
作業手順もシンプルでつまってもすぐ試せる
【作業手順とポイント】
- シンクの目皿、トラップを取り外す
・取り外した目皿やトラップ、シンク内にある三角コーナーや食器類などはシンクの外に全て出します。 - タオルを排水口に軽くつめる
・タオルの端を排水口に軽くつめ、反対側のタオルの端はシンクの外に出しておきます。 - 60℃のお湯をシンク半分まで溜める
・給湯パネルの設定温度を60℃に設定してお湯を溜めて行きます。シンクの半分位になるまで溜め続けましょう。 - タオルを引き抜き、一気に流す
・外側に出しておいたタオルの端を引っ張って栓を抜き、一気に流して行きます。
特に購入して準備する物はありませんので、すぐにでも実践することができるお手軽な解消法です。
注意点を守って効果的に排水口を直そう!
この方法は手軽で効果的ですが、誤ったやり方は排水設備を傷めたり、水漏れを引き起こす原因にもなります。
以下の点には十分注意して行いましょう。
■ 60℃以上のお湯は使わない
- 沸騰した熱湯は絶対に流さないでください。
少量であれば問題ありませんが、シンク半分ほどの大量の熱湯を流すと、排水管が変形したり、排水ホースから水漏れを起こす危険性があります。
■ 床下の排水管がつまっている場合は使用NG
- 床下の排水管でつまりが起きているときにこの方法を行うと、大きな水漏れにつながる恐れがあります。
市販洗剤で排水口つまりを直す効果的なテクニック
市販の排水洗浄剤を「最大限に効果的に使う」ためのテクニック
■ 用法・用量を正しく守る
- 市販洗剤にはすべて使用方法と使用量が明記されています。
これらは、洗剤メーカーの研究開発チームが最も効果が出るように綿密に設定した基準です。 - 「多く入れればもっと効くだろう」と自己判断で使うのはNG。
洗浄効果が上がるどころか、逆に配管を傷めたり、薬剤が無駄になるだけです。
正しい用法・用量を守ることが、洗剤の効果を最大化する一番の方法です。
■ 排水口まわりをできるだけキレイにしてから使用する
- つまり解消を目的に洗剤を使うときは、まず排水口まわりの目皿やトラップなどを掃除し、余分なゴミや汚れを取り除いてから行いましょう。
- 排水口が汚れていると、洗剤の洗浄力が表面的な汚れに分散され、肝心のつまり部分に十分な効果が届きません。
それでは市販洗剤の解消法いくつがご紹介します。
【排水口掃除の定番】パイプユニッシュでつまり解消法
排水の流れが悪くなったとき、家庭でできる対処法のひとつが市販のパイプクリーナーの使用です。
ここでは、「パイプユニッシュPRO 400g」を例に、基本的な使い方をご紹介します。
■ 作業手順
- 目皿・トラップを外し、排水口まわりを清掃する
・まずは排水口のゴミや汚れを取り除きましょう。
・ここを掃除しておくことで、薬剤の洗浄力がつまり部分に集中します。 - ボトルの約1/3(約130g)を排水口に直接注ぐ
・キャップを開けて、ゆっくりと薬剤を排水口に流し込みます。
・目安はボトルの1/3程度。説明書の指示に従ってください。 - 15〜30分ほど放置する
・時間を置くことで、薬剤がつまりの原因(油汚れやヌメリ、軽いヘドロなど)を分解します。 - たっぷりの水で一気に洗い流す
・最後に、水を勢いよく流して薬剤と汚れを洗い流します。
・水がスムーズに流れるようになっていれば成功です。
市販洗剤の中では強力なピーピースルーFの効果とは?
ピーピースルーFは、市販の洗浄剤の中でも特に洗浄力が高く、油汚れや軽度のつまりに効果的です。
■ ピーピースルーFの基本的な使い方
【作業手順】
- 目皿・トラップを外し、排水口まわりをキレイにする
・汚れやゴミを取り除いてから行うことで、洗浄成分がつまりの原因に集中して作用します。 - ボトルの約1/4を排水口に投入
・使う量の目安は1回あたり、ボトルの1/4程度です。 - 40℃程度のお湯を500mlゆっくり注ぐ
・40℃のお湯で薬剤が反応しやすくなり、効果が高まります。 - 30分間放置する
・この間に、ピーピースルーFが排水管内の汚れやぬめりをしっかり分解していきます。 - たっぷりの水でしっかり洗い流す
・薬剤を残さず流すよう、勢いよく水を流しましょう。
意外!カビキラーでもつまりを除去できる!?
お風呂掃除の定番アイテム「カビキラー」ですが、実は台所の排水口にも使えることをご存知ですか?カビキラーは塩素系のカビ取り剤で、カビだけでなく、排水口の油汚れやヌメリなども分解する効果があります。
専用の排水洗浄剤が手元にないときでも、代用品として十分役立ちます。
■ 使用時の注意点
- 換気をしっかり行う
カビキラーは塩素系成分を含んでおり、使用中に強い刺激臭が発生します。必ず換気扇を回す、窓を開けるなどして十分な換気を確保してください。 - 他の洗剤との併用は絶対NG
特に注意したいのが、酸性洗剤との併用。塩素系の洗剤と酸性洗剤が混ざると、有毒な塩素ガスが発生して非常に危険です。
正しく使える?排水口つまりでDIYと言えばラバーカップ
DIYでつまりを解消する定番アイテムといえば、スッポンとも呼ばれるラバーカップです。
市販の洗剤を使っても解消しない場合は、ラバーカップを使って物理的につまりを取り除く方法があります。
ラバーカップは手頃な価格で、100円ショップやホームセンターなどで簡単に購入できるのも魅力です。
正しく使わないと効果半減で台所つまりが解消できない
ラバーカップは、水の流れが悪くなったときに頼れるシンプルで効果的なつまり解消ツールです。
ただし、「押すよりも引く」こと、「密閉させる」ことが成功のカギ。
これができないと効果が大きく下がってしまいます。
■ 作業手順とポイント
- シンクの目皿・トラップを取り外す
・目皿やトラップ、シンク内のものはすべて取り除きます。
・ゴミ受けや三角コーナー、食器なども一度外に出しましょう。 - シンクに水を溜める(ラバーカップのゴムが浸かる程度)
・水がないと空気が入り、密閉できず効果が出ません。
・ゴム部分がしっかり水に浸かるまで、シンクに数cmの水を溜めておきましょう。 - ラバーカップを排水口に密着させてゆっくり押す
・隙間ができないように、垂直に押し当てて密着させます。
・この時、勢いよく押さずゆっくりと押し込むのがポイント。 - 真上に一気に引き上げる(ここが本番!)
・ラバーカップは「引く」時に力を入れます。
・排水のつまりを引っ張り出すイメージで、勢いよく真上に引き上げましょう。 - 押し引きを繰り返す(15〜20回程度)
・15〜20回試しても改善しない場合は、「ラバーカップでは対応できないつまり」と判断し、他の方法を検討しましょう。
台所の予防法3選!これで排水口つまりを起こさせない
台所をつまらせない為の予防法を3つご紹介します。ぜひお役立てください。
洗い物の最後に多めの水を流してつまり原因を溜まらせない

洗い物の後に60秒間水を流すことで、油や汚れを液体のまま排水管の外まで押し流せます。
油も最初は液体なので、しっかり水で流すことで、排水管や排水桝に汚れや油が溜まるのを防げます。
実際、多くの家庭では60秒間の水流で油や汚れが敷地外まで流れていきますので、簡単にできる予防法としておすすめです。
排水口の目皿を外して流さない!こまめな清掃がポイント
「目皿があると排水が流れにくいから」と思って、目皿を外してしまう方がいますが、これは非常にリスクが高い行為です。
目皿がないと、大きなゴミや食材カスが排水管の奥まで流れてしまい、排水口から遠い場所で詰まることが多くなります。
詰まりが奥で起こると、自分で直すのが難しくなり、業者に依頼した場合の修理費用も高額になりやすいです。
目皿は、掃除をするとき以外は必ず付けたまま使用してください。
もし排水の流れが悪いと感じたら、目皿やネットの清掃頻度を増やして、こまめに掃除することが重要です。
【月1回】台所シンクにお湯を溜めて一気に流す
「自分で台所の排水口つまりを解消する3つの方法」で紹介した「お湯とタオルを使った方法」です。この方法は予防にも使え、月1回位のタイミングで行うと効果的な予防法となります。
プロの台所つまりの解消法!事例を基に作業内容を解説
台所のつまりで実際にプロが行なった解消法を紹介いたします。
排水口に落ちたスポンジを吸引力抜群なローポンプで回収

ある現場で、排水口にサイコロ大のスポンジが詰まってしまったケースがありました。
このような固形物はラバーカップよりも強力な吸引力を持つ「ローポンプ」が効果的です。
ローポンプとは、ラバーカップや真空式パイプクリーナーの強力版のような器具で、非常に高い吸引力を発揮します。
作業はシンプル。
シンクに水を溜めてローポンプを排水口にセットし、取っ手を一気に引くと…なんと、一発でスポンジを吸い上げて取り除くことができました!
トーラーと高圧洗浄で台所の流れが悪いのをスッキリ解消

床下排水管で詰まりが発生した現場です。
このつまりの解消には「トーラー」と「高圧洗浄」を使いました。
トーラーとは、ワイヤーを排水管内に入れて、つまりを直接砕く器具のことです。
一方、高圧洗浄は「洗管ホース」と呼ばれるホースを排水管内に入れ、ホース先端から噴射される高圧の水でつまりを吹き飛ばします。
作業の途中、ワイヤーを約3m入れたところでつまりに当たり、回転させてじっくり砕くことにしました。
一度ワイヤーを引き抜くと、先端のドリル部には乳白色の塊がびっしり付着していました。
これは油脂の固まりです。
先端をきれいに洗浄し、再びワイヤーを入れて回転させると、しばらくして急にワイヤーがスムーズに入るようになりました。
油脂の塊に穴が空いたため、その後に高圧洗浄を行い、管内を洗浄してつまりを完全に解消しました。
桝が溢れる緊急事態!蓄積した油・脂の塊が原因でつまり発生

排水桝から水が溢れている現場でした。原因は大量に溜まった油脂の塊です。
トーラー作業中には、剥がれ落ちた油脂の塊が次々と流れてきました。
流れてきた油脂の塊が先の排水管へ流れ込まないように、作業員が丁寧に拾い上げながら作業を進めました。
続いて行った高圧洗浄では、白濁した水が流れ出てきました。
これは油が溶けて水と混ざったものです。この水が透明になるまで高圧洗浄を繰り返しました。
管内にはかなり多くの油が残っていたようで、高圧洗浄だけで約1時間かかりましたが、無事につまりを改善することができました。
まとめ
台所排水口つまりの解消法と予防法を見てきましたが、つまったものをどう解消するかよりも如何にしてつまらせないかの方が大事です。
その為にも予防が大事であり、今回ご紹介した予防法は簡単で誰でもできる内容なので、ぜひ実践してみてください。



