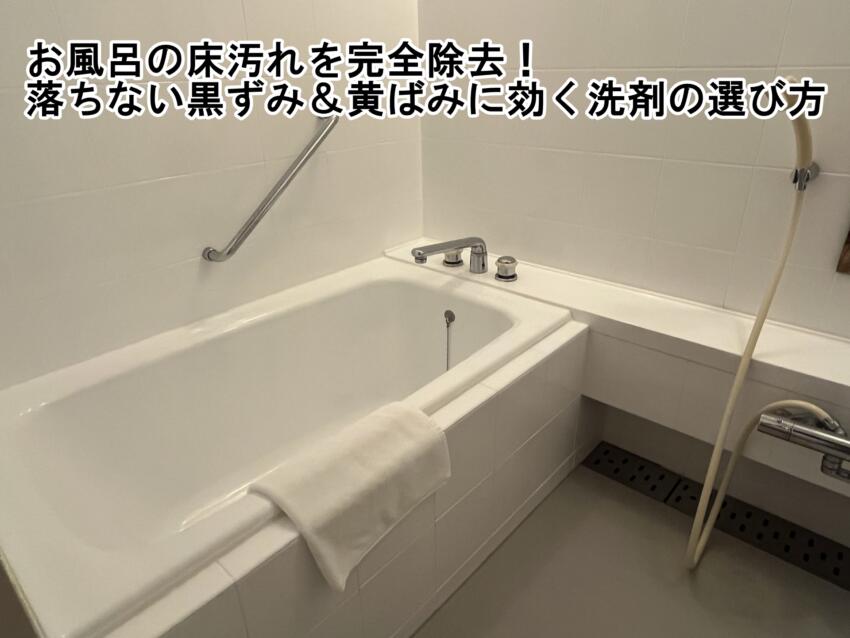
お風呂の床にできる黒ずみは、せっかくのリラックスタイムの邪魔になってしまいますよね。
1日の疲れを癒す場所だからこそ、お風呂はいつでも清潔で気持ちよく使いたいものです。
床の汚れが気になると、なんとなくお湯にゆっくり浸かる気分にもなれず、もったいないですよね。
そこで今回は、「きれいなお風呂の床」を目指して、黒ずみの正体とその効果的な落とし方についてご紹介します。
この記事では、黒ずみの原因をタイプ別に解説し、それぞれの汚れに合った洗剤の選び方や、効率的な掃除方法を詳しくお伝えします。
「落ちない」とあきらめていた床の汚れも、正しく対処すれば驚くほどすっきり落とせるかもしれません。
原因を見極めて、気持ちのよいバスタイムを取り戻しましょう。




お風呂の床の汚れの原因と特徴

お風呂の床の黒ずみは汚れです。
長年の使用によって変色してしまった場合、黒ずみだけでなく黄ばみが目立つこともあります。
こうした汚れも、まずは掃除で落とせるかどうか試してみましょう。
経年汚れだからといってあきらめず、適切な洗剤と掃除方法を試すことで、意外とすっきり落ちることもあります。
丁寧に掃除をして落ちない場合はハウスクリーニング業者の手を借りるという方法もあります。
お風呂の黒ずみの原因は体から出る皮脂やたんぱく質の汚れとメイクやヘアケア用品に含まれる油分が原因といえます。
他にも黒カビや石鹸カスなど床に黒ずみを作る汚れがあります。お風呂の床の汚れにはどのようなものがあるか見ていきましょう。
皮脂、メイク汚れ、ヘアケア用品の成分
お風呂は体を洗うだけでなく、メイクを落としたり、コンディショナーやヘアクリームを使ったりすることも多い場所です。
そのため、床に付着する汚れは皮脂だけでなく、化粧品やヘアケア製品に含まれる油分が大きな原因となります。
これらの油分は、付着してすぐであれば簡単に落とせることが多いですが、時間が経つと徐々に堆積し、やがて落としにくい頑固な汚れに変化します。
気づいたときには、黒ずみとして床に定着してしまっている、ということも少なくありません。
石けんかす

石けんかすは石けんやボディソープの成分が固まって残った汚れです。石けんかすには2種類あります。
石けんを使った時に皮脂の成分と石けん(ボディソープ)の成分が結びついて発生します。
石けんはアルカリ性(※)ですが皮脂は酸性です。
皮脂を含んだ石鹸カスの性質は酸性であるのでこの汚れは「酸性石けん」と呼ばれています。
もう一つは「金属石けん」と呼ばれる汚れです。
水道水に含まれているカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分と石けんが結びついてできる石鹸カスで性質はアルカリ性です。
お風呂の床に白い固まりや黄ばみがみられる場合はこの金属石けんの可能性があります。
「酸性石けん」「金属石けん」とも落としにくい汚れです。
汚れが長期間放置されている場合はこの2つの汚れが混ざって複雑な汚れになり黒ずみの原因にもなってしまう事もあります。
(※)ボディソープには弱酸性のものもあります
水垢
水滴が残ったままの場所では、時間の経過とともに水分だけが蒸発し、水道水に含まれるミネラル分が白い固形物として表面に残ります。これが「水垢」です。
水道水には、カルシウム・マグネシウム・炭酸・鉄イオンといった無機成分が含まれています。
特に、床の色が黒っぽい場合は、この白い水垢が目立ちやすくなります。
また、床だけでなく、ステンレス製の蛇口などにも水垢は白く目立って付きやすく、見た目にも気になります。
さらに、浴槽の縁などでザラザラとした手触りを感じる場合も、水垢が付着しているサインです。
黒カビ

黒カビはお風呂に繁殖するしつこいカビです。
その名前の通り黒色でタイルの目地やパッキン、排水溝に発生して放置すると根を張って取れない汚れになってしまいます。
塩素系漂白剤などで除去してもいつの間にかまた発生する厄介なカビです。
黒カビは床だけでなく、壁や天井にも発生します。
特に天井などの高い場所は掃除がしにくいため、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、天井に発生したカビは胞子を空中にまき散らし、床や浴槽、壁など他の場所へのカビの再発を引き起こす原因となります。
そのため、床や浴槽の黒カビをしっかり除去するには、天井や壁もしっかり掃除することが不可欠です。
黒カビが発生しやすい条件は「20~30℃の温度」と「70%以上の湿度」 でお風呂はこの条件にぴったりです。
カビの栄養になる石けんかすや皮脂などの汚れもあるためお風呂は黒カビが繁殖しやすい条件が揃っています。
黒カビはアレルギーやぜんそくの原因にもなりますので健康のためにも黒カビは除去しておきたい汚れです。
赤カビ
赤カビはオレンジっぽいピンク色をしたぬめりです。
お風呂だけではなく洗面台やシンクなど水があるところに発生します。正確にはカビではなくロドトルラと呼ばれる酵母菌などがその正体です。
特徴は2~3日で繁殖してしまうことです。
黒カビのように落としにくいわけではなく浴室用の中性洗剤とスポンジでこすれば落とせる程度の汚れでもあります。
しかし再発生することも多く完全に除去するには殺菌が必要になります。


汚れにあった洗剤を使うお風呂の床の掃除方法

汚れにはそれぞれ性質があります。酸性汚れはアルカリ性の洗剤でアルカリ汚れは酸性の洗剤を使います。
汚れとは逆の性質の洗剤で汚れを中和して緩めて落とす方法です。
床の汚れにはアルカリ汚れと酸性汚れがありますのでそれぞれの汚れに適した洗剤を使い分ける必要があります。
床の汚れ一覧表
床の汚れの性質と、汚れを中和する洗剤を一覧表にしました。
| 汚れ | 性質 | 洗剤・洗浄剤の性質 |
| 皮脂・メイク・クリームなど | 酸性 | アルカリ性(重曹・酸素系漂白剤) |
| 石けんカス(酸性石けん) | 酸性 | アルカリ性(重曹・酸素系漂白剤) |
| 石けんカス(金属石けん) | アルカリ性 | 酸性(クエン酸・お風呂用酸性洗剤) |
| 水垢 | アルカリ性 | 酸性(クエン酸・お風呂用酸性洗剤) |
| 黒カビ | 酸性 | アルカリ性(重曹・酸素系漂白剤・塩素系漂白剤) |
| 赤カビ | 酸性 | アルカリ性・中性(重曹・お風呂用洗剤) |
それぞれの汚れの落とし方を詳しく見ていきましょう。
皮脂汚れはお風呂用洗剤か酸素系漂白剤のつけおき洗い
お風呂の床の黒ずみの原因になる皮脂やメイクなどの汚れはお風呂用洗剤で洗ってみましょう。
お風呂用洗剤で取れない場合は酸素系漂白剤でつけおき洗いがおすすめです。
お風呂用洗剤でこすり洗い

床がタイルの場合は滑り止めのために表面にある微細な凹凸に汚れが入り込んで黒ずみになっています。
樹脂製の床の場合はやはり凹凸の凹部分や凸の根元に汚れが残りやすくなります。
ブラシを使って丁寧に汚れを洗いましょう。
お風呂用洗剤には弱アルカリ性のものの方が多く中性洗剤は少ないのが現状です。
皮脂汚れなど黒ずみは酸性の汚れと考えられますのでお風呂用洗剤で洗います。
中性洗剤であっても界面活性剤が汚れを浮き上がらせるため洗ってみることをおすすめします。
オキシクリーン(酸素系漂白剤)でつけおき洗い

お風呂用洗剤で洗っても黒ずみが取れない場合は酸素系漂白剤を溶かしてつけおき洗いをしましょう。
<準備>
オキシクリーン(酸素系漂白剤)・ブラシ・ゴム手袋・洗面器かバケツ
●お風呂の床をつけおきする場合は、2重にしたナイロン袋に水を入れて排水口にのせ、水が流れるのを防ぎます。
<パック手順>
- 洗面器かバケツに50℃くらいのお湯を入れその中にオキシクリーンを入れてよく溶かす(※)
- 床に1cmくらいの深さで40~50℃のお湯をためます。
お風呂の床は排水溝に向かって勾配がついているので注意すること - たまったお湯に①で溶かしたオキシクリーン液を入れてよく混ぜ合わせ3~6時間おく
- 時間が来たら排水口のナイロン袋を外して液を流す。
その後にブラシでこすって水で洗い流す
※【参考】お風呂の床の面積が4㎡(約1.2坪)の時に1cm深さの水を入れると40L入ります。
日本版オキシクリーンの場合は280gが投入の目安になります。
石けんかすはアルカリと酸性が混ざっている可能性あり
石けんカスによる汚れは、アルカリ性と酸性の汚れが混ざり合ってできているため、非常に落としにくいのが特徴です。
その汚れの色もさまざまで、白・黄色・グレー・黒など、場所や状態によって見え方が異なります。
石けんカスは、皮脂汚れの掃除をした際に一緒に落ちることもあれば、水垢を落とす作業の中で取れることもあります。
そのため、まずは他の汚れを落とした後に、まだ残っている部分を確認することで、石けんカスかどうかの判断がしやすくなります。
床の黒ずみを取るために浸け置きした後に残る汚れはアルカリ性の汚れです。
カビキラーやカビハイターで洗った汚れの後に残る白っぽい汚れもアルカリ性の汚れです。
アルカリ性の汚れはお風呂の水垢用洗剤 かクエン酸で落としましょう。
【注意】
水垢用洗剤やクエン酸は酸性です。塩素系漂白剤と混ざると有毒なガスが発生しますので混ざらないように十分注意が必要です。
水垢は酸性のクエン酸水で掃除

白や黄ばみがある水垢はアルカリ性の汚れなので、酸性のクエン酸水を吹きかけて落とします。
長年堆積した汚れの場合は一度や二度の掃除では取れないものです。
気長に何度も掃除を繰り返すことが必要になります。
軽い水垢の場合はクエン酸水を吹きかけてこすると落ちる場合もあります。
しつこい水垢の場合はクエン酸を吹きかけてパックをして水垢にクエン酸が浸透し中和する時間を取る方が落としやすいでしょう。
<準備>
水200cc クエン酸小さじ2 ティッシュペーパー ラップ スプレーボトル ゴム手袋
<パック手順>
- スプレーボトルに入れた水にクエン酸を入れ、よく振って混ぜ合わせる
- 水垢がある場所に①をスプレーし、ティッシュペーパーを貼り付け、再度①をスプレーする
- パックした場所を乾燥しないようにラップで覆い10分置く
- 時間が来たら、ラップを外し、ブラシでこすって水で洗い流す
黒カビはアルカリ洗浄剤で掃除

黒カビ落しの定番は塩素系漂白剤のカビキラー・カビハイターではないでしょうか。
強いアルカリ性の塩素系漂白剤はカビ取りに向いた洗浄剤です。
カビがこすったくらいでは落ちないのはカビが色素を作って目地やパッキンの奥まで根を張ってしまうためです。
塩素系漂白剤は黒カビの色素を分解しカビの組織を破壊して掃除をします。
次亜塩素酸ナトリウムが入っているため除菌力もありしっかり掃除をすればカビの菌を残さずに掃除できます。
しかし予防効果はないためカビが発生するごとの掃除は必要です。
お風呂の床の黒ずみの原因となる場合はタイルの目地に深く入り込んでいる場合です。
塩素系漂白剤をかけてブラシなどでこすると概ねのカビは取れます。
しかし取れない場合は漂白剤が乾かないようにパックをして時間を置き洗い流しましょう。
【注意!】
カビキラーやカビハイターなどの塩素系漂白剤には「混ぜるな危険」の表示があります。
クエン酸や酸性の水垢用洗剤と混ぜると塩素ガスが発生し人体に危険を及ぼします。
一緒に使用したり混ざらないように十分に注意しましょう。
タイルの目地のパックの仕方

目地をパックする方法を説明しますがパッキンや浴室の隅、入り口のサッシの下部などのカビ取りにも使える方法です。
<準備>
カビキラーかカビハイター泡タイプ(塩素系漂白剤)・細長く切ったティッシュペーパー・ラップ・ゴム手袋
<パック手順>
- 換気扇を回し窓があれば開けて換気をよくする
- 取れない黒カビのある目地や場所にカビキラーを吹きかけ細長く切ったティッシュペーパーを貼り付ける。
その上から再度カビキラーをかける - パックした場所を乾燥しないようにラップで覆い20~30分置く
- 時間が来たらラップとティッシュを外してブラシでこすって水で洗い流す
※ブラシでこする際は飛沫が目に入らないように注意する
ナチュラル洗剤の場合は重曹を使おう

黒カビは酸性汚れですのでナチュラル洗剤を使う場合は重曹で掃除をします。
重曹スプレー(※)を吹きかけブラシでこすって落とします。
カビが取れない場合は重曹ペーストを作りパックして落としましょう。
(※:水100ccに重曹小さじ1杯を溶かしたものをスプレーボトルに詰める)
<準備>
水大さじ1 重曹大さじ3 ラップ ゴム手袋
<パック手順>
- 水と重曹をペースト状になるまで混ぜ合わせる
- カビの上に塗り、乾燥しないようにラップで覆い30分置く
- パックした場所を乾燥しないようにラップで覆い20~30分置く
- 時間が来たら、ラップを外し、ブラシでこすって水で洗い流す
重曹と塩素系漂白剤のどちらが良くカビを落とすかといえば塩素系漂白剤の方がしつこいカビをおとすのには向いています。
重曹でどうしても落ちない場合は塩素系漂白剤を試してみてもよいのではないでしょうか。
赤カビは酸素系漂白剤で掃除

赤カビは頻繁に発生し繁殖力が強いのですが落としやすいという特徴があります。
中性洗剤をかけてスポンジでこすると落ちてくれます。
しかし再発を防ぐには除菌・殺菌できる洗い方がよいでしょう。
おすすめの掃除方法は酸素系漂白剤です。
酸素系漂白剤は粉末の漂白剤でオキシクリーンやワイドハイター粉末などです。
赤カビが発生しているところに酸素系漂白剤を適量まいて水を含ませたスポンジかブラシでこすり洗いしそのまま30分程度放置します。
その後にシャワーで洗い流しましょう。
もちろんカビキラーなどの塩素系漂白剤でも落とすことができます。
重曹でも汚れを落とすことはできますが重曹には殺菌や除菌の機能がないので再発の防止を考えればオキシクリーンやカビキラーでの掃除をおすすめします。
取れない黒ずみや黄ばみはどうやって落とす?
汚れに合った洗剤を使っていても、黒ずみや黄ばみがなかなか落ちないことがあります。
特にタイル床の黒ずみが頑固な場合は、クリームクレンザー(例:ジフなど)とブラシを使ってこすり洗いを試してみると効果的です。
ただし、注意が必要なのは床の素材が樹脂製の場合です。
クリームクレンザーの研磨剤やブラシによって、細かい傷がついてしまう可能性があるため、使用はおすすめできません。床材に合った方法で、無理なく安全に掃除を行いましょう。
掃除のときはお風呂の床の素材や形状も考える
お風呂の床の掃除をする際にはどのような洗い方が我が家のお風呂の床にぴったりかを考えてみましょう。
お風呂の床は滑り止めのために凹凸があります。
スポンジでは洗いきれない場合はブラシでの掃除やつけおき洗いが有効かもしれません。
また、タイル目地は汚れが付きやすいところでもあります。
小さなブラシで洗いにくい場合は思い切ってベランダで使うような長い柄のブラシで目地にそって縦横をきっちり洗うのが効果的かもしれません。
洗い残しが積み重なると取れない汚れになります。
無理なく全体を洗える工夫をしてみましょう。
日常的な掃除と定期的な掃除の仕方を変える

お風呂掃除は毎日隅から隅まで洗うのは大変な作業になります。そのため毎日洗う部分とまとめて掃除する部分ができてしまいますね。
日常的に行いたい掃除と定期的に行いたい掃除を表にしました。
| タイミング | 掃除内容 |
| 日常的な掃除 | ・浴槽を洗う ・壁と床をお湯で流す(床の四隅はとくに注意) ・スクイージーで水を切る(乾燥を早める・水垢防止) ・50℃のお湯を壁や床にかける(黒カビ対策) ・窓や戸を閉めて換気扇は回しっぱなしに |
| 週1~2回の掃除 | ・床のこすり洗い ・棚やボトルの下を拭く ・椅子や洗面器を洗う |
| 月1~2回の掃除 | ・壁の高い位置や天井の掃除 ・換気扇のホコリ取り ・浴室乾燥機のフィルターは1~2か月に1度は掃除 |
お風呂の床の汚れの予防
お風呂の床は、汚れがたまりやすい場所のひとつです。
体を洗ったときに落ちた皮脂や石けんの成分などが、十分に洗い流されないと、床に残ってしまいます。
こうした汚れは、1回ごとの量はごくわずかで目立たないものですが、日々の蓄積によって徐々に黒ずみや黄ばみとして現れてくるのです。
お風呂を出る際にはお湯で皮脂や石けんかすを流すという意識をもって床を流しましょう。
流す際には壁際から排水口に向かって流すのが鉄則です。
また床にカビや水垢を残さないためにスクイージーでの水切りをおすすめします。
床が早く乾くことで黒カビや赤カビを防げますし水滴がなくなることで水垢の発生を防げるためです。
まとめ
今回は、お風呂の床の黒ずみ落としを中心に、床に付く汚れの原因と効果的な掃除方法をご紹介しました。
床の汚れは、普段はあまり気にならないこともありますが、一度気になり始めると何とかしてきれいにしたいと思うものですよね。
お風呂は、1日の疲れを癒やす場所であると同時に、日々の汚れを落とすための場所でもあります。
入浴時に落とした汚れを浴室内に残さず、きちんと流しておきたいものです。
まずはお風呂の汚れをリセットして、そこから汚れをためないための掃除習慣を始めてみてはいかがでしょうか。



